「かんたんかんぽう」というのは、私たちが提唱している シンプルかつ効果的かつ再現性のある 漢方薬の選びかたと使い方のことです。
何に比べて簡単かですが、これまでに漢方の専門家が習い伝えてきた たとえば 五行説/五臓六腑の五行配当とそれに基づく複雑な相生相克 であるとか、胃とか腎っていうけど我々が思っている胃とか腎ではないとか、六病期における直中の少陰だの合病と併病の相違、少陽が先か陽明が先か……どうです、読んだだけで どうもこれはシンプルな話ではないな、ということがわかってもらえると思います。
よく漢方の習い始めに指導されることとして「これまで習った医学のことは忘れろ!西洋医学と東洋医学は考えかたからして全く違うのだから、漢方のことを考えるためには、西洋医学はむしろ邪魔なんだ!心を真っ白にしていちからやり直してください」。おいおいなんか大変なことになってきたぞ、という感じがしませんか?
だから漢方薬をつかうことに二の足を踏んじゃうひとが一定数いらっしゃると思うんです。そりゃそうですよね。そもそも言ってることが意味わかんないし、勉強しようかなと思ったら「これまでの常識は捨てろ」とか言われるし……正直ハードルが高すぎると思います。漢方を使いだして20年の私から見てもそう見えます。
でも勿体ないですよね。だって漢方薬は実際に色んな症状を改善しますし、西洋薬の得意としない領域でも効果がある場合もある。ときよっては、長年 悩んでいたことがビックリするくらい早く解決したりする。上手に使えるとすごく便利なんです。でも、ムズカシイことを勉強しないと使えないのなら、あまり積極的に使う気にはなりませんよね。
ではどうすれば良いのか。ひとつには、上記のような複雑な概念はひとまず横にどけておき、漢方薬の中身……つまり漢方薬を構成している生薬の種類からその効果と、それが効きやすいひとを考えることが出来ます。例えば入っているシナモン(桂皮、桂枝)は何をしてるのか、乾かした生姜(乾姜)が入ってるから冷えを治すんだなとか、川芎(センキュウ)が入ってるなら頭部と体幹の血流を良くするんだな、とか。なんとなくイメージがわきませんか?もうひとつは、難しい専門術語をわかりやすい日本語で表現することです。長くなるからひとつだけ例にあげてみると「直中の少陰とはつまり、元気な人なら風邪を引いたとき、身体の表面近くで頭痛や肩こりがして熱が出るもんだけど、疲れていて弱っているひとが風邪にかかったときは、いきなり全体倦怠感や四肢の冷え、下痢といった症状が出てとにかく横になりたくなる、そゆこと」。これなら意味がわかりますよね。
専門家は専門家としての学びかたがありますが、そうでない一般の方や、東洋医学専門ではない医療関係者には上記のような学習方法が適していると思います。かんたんかんぽう は、そういう方々の学びをお手伝いするサイトです。ゆっくりとお伝えしていきます。
次回は、みなさんも聞いたこともあるだろうし、使ったこともあるかもしれない「芍薬甘草湯」について解説してみたいと思います。甘草湯って、聞いたことありますか?それに芍薬を足すだけで芍薬甘草湯に、さらには……「甘草湯から始める“かんたん漢方クエスト”」。生薬を1つ足すたびに、処方がレベルアップしていく様子を、ゲーム感覚でお届けします!

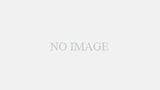
コメント